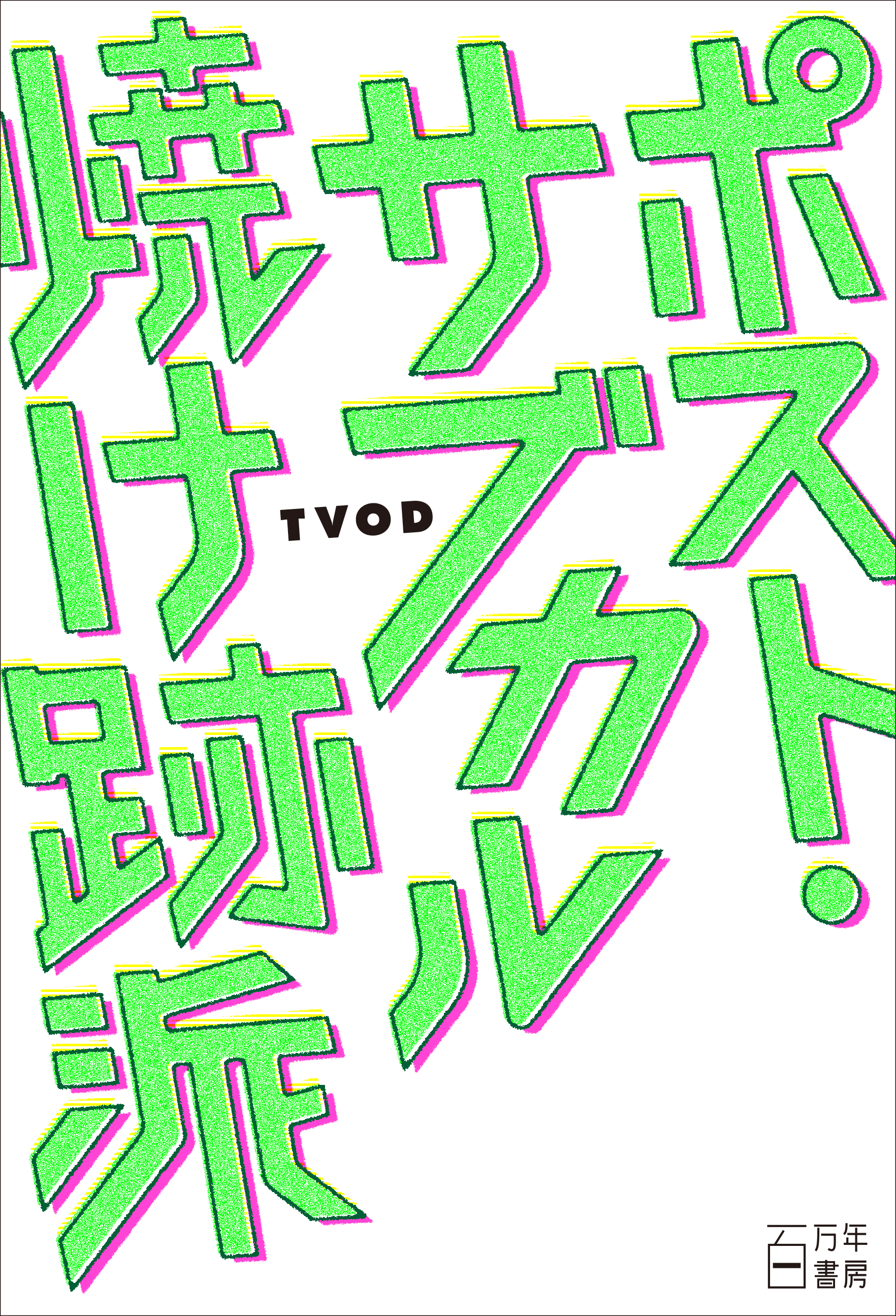
ポスト・サブカル焼け跡派
| 著者名 | |
|---|---|
| 発売日 | 2020年01月31日 |
| 価格 | 2400円+税 |
| 判型 | 四六 |
| ISBN | 9784910053127 |
【目次】
プロローグ コメカ(TVOD)
第1章 カウンターからサブカルチャーへ(1973-1978)
矢沢永吉 アメリカ化された「天然」の天才
沢田研二 ポップな記号に成りきること
坂本龍一 消費されるイデオロギー
第2章 消費社会空間の完成、ジャパン・アズ・ナンバーワン(1979-1988)
ビートたけし 消費社会で勝ち抜くこと
戸川純 女たちのサブカルチャー
江戸アケミ バブル・ニッポンにおける「もがき」
第3章 リアルと無意識(1989-1998)
フリッパーズ・ギター 「本当は何か本当があるはず」
電気グルーヴ 諧謔・暴力・快楽
X JAPAN 90年代最強の記号
第4章 ネオリベ、セカイ系、右傾化(1999-2010)
椎名林檎 自意識と生存戦略
KREVA コミュニタリアンとネオリベラリズムの狭間で
バンプ・オブ・チキン セカイ系J-ROCK
第5章 「孤児」たちの時代へ(2011-2019)
星野源 「煩悶青年」への回答
秋元康 ポスト戦後のゲームマスター
大森靖子 たったひとりのあなたに届けるということ
エピローグ
焼け跡から見た風景--あとがきにかえて パンス(TVOD)
年表・サブカルチャーと社会の50年
【プロローグ】
いま、この国は焼け跡化しつつある。
テレビをつければタレントたちが「日本スゴイ」とわめき立て、御用学者たちは日本経済の劇的な復活を説き、与党政治家たちは愛国心の重要性と憲法改正の必要性を訴え、総理大臣は国民とともに「美しい国」をつくっていくと嘯く。ひとつのメルクマールとしての2020年東京オリンピック開催に向けて、この国は愛国的なナルシシズムをひたすらに増幅させ続けている。
だが、実際のこの国の有り様は、本当にそんなに「美しい」ものだろうか? レイシストたちがネットや路上で差別を撒き散らし、大企業優遇税制により富裕層が内部保留を増やし続ける一方、庶民は消費増税までされて搾り取られ、各地での災害復興は進まないまま他地域の人々に忘却され、首相の「アンダー・コントロール」の言葉とは裏腹に、福島第一原発事故の収束見通しは立っていない。
端的に言って、一時は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」とまで囃し立てられたかつての日本の繁栄がもはや失われたことを直視できず、「美しい国」というチープなナルシシズムに逃げ込んでいるというのがいまのこの国の実態、偽らざる姿だと僕は思う。そしてその幻想に国家全体がトリップすればするほど、国民の暮らしは貧しく悲惨なものになっていく。人々がかつての栄光を幻視しそれに浸れば浸るほど、現実の世界の火の手はますます燃え上がり、焼け跡が広がり続けていく。
TVODは1984年生まれの男性ふたりで構成されたユニットである。僕らはバブル景気に沸く80年代後半に幼少期を送り、連続幼女誘拐殺人事件、阪神大震災、地下鉄サリン事件、神戸連続児童殺傷事件と社会不安が続いた90年代に少年期を過ごし、アメリカ同時多発テロ事件と続くイラク戦争をテレビ画面の向こうに眺めながらゼロ年代に青年になった。20世紀にギリギリ間に合ってしまったせいで、旧時代の価値観を抱えながら21世紀を生きることになった最後の世代が、僕らの世代なのではないかと思う。
僕もパンスもいわゆるひ弱な文系男子の類であり、そういったタイプの人間のご多分に漏れず、少年の頃からさまざまなサブカルチャーに触れて日々をやり過ごしてきた。ふたりともとりわけポップミュージックに思い入れが強く、はじめて出会ったゼロ年代中盤の大学生の頃、80年代ニューウェーブの話で盛り上がったことを今でもよく憶えている。海の向こうでバグダードが爆撃され、サダム・フセインがアメリカ軍に捉えられていたときにも、僕は古今東西のサブカルチャーを追いかけることに熱中し、古本屋やレコード屋に通い詰めてばかりいた。
1970年代以降、高度経済成長を経て、日本は世界有数の経済大国となっていった。その消費社会化のプロセスの中、主に60年代カウンターカルチャーが消費文化化されていく形で、国内のサブカルチャーの生産/消費が隆盛し、同時に海外のポップカルチャーの「サブカル的な」受容が日本に広がっていく。僕やパンスが「間に合ってしまった20世紀」とは、つまりそういう時代のことだ。カウンターカルチャー、革命、「68年的なもの」、そういった夢がすべて潰えた後の世界で、終わらない消費社会の中で、どこまでもサブカルチャーの消費に明け暮れ続ける……70年代以降の日本社会は、ずっとそんな感覚の中にあったんじゃないかと思う。「もう“デカイ一発”はこない」(鶴見済『完全自殺マニュアル』)。夢が終わった後の世界で、終わらない日常をサブカルチャーとともにやり過ごし続けること。いつまでも戯れ続けること。
だが、どうやら状況は変わりつつあるらしい。バブル崩壊、世界金融危機、東日本大震災、その果てに訪れた経済危機から目を逸らし、「美しい国」という夢にトリップするために、この国は手あたり次第に大量のドラッグをボリボリと噛み砕き、飲み下し続けている。革命の夢から醒め、終わらない退屈な消費社会の中でサブカル消費に明け暮れていたはずのあの日々は幻だったのか? 消費文化を通じた戯れの向こう側にあるのは、貧しく荒れ果てた社会と安っぽく陳腐なファシズムの夢でしかないのだろうか?
いま、この国は焼け跡化しつつある。
焼け跡の上に、貧しく陳腐な夢が立ち上がりつつある。
本書で僕たちTVODは、20世紀にギリギリ間に合ってしまった世代なりの視点で70年代以降の日本のポップミュージックの軌跡を辿り、現在に至るまでのひとつの文化的精神史を描くことを試みた。「ナンバーワン」だった国が没落し、焼け跡化していく中で育った人間として自分たちが考えてきたことを、20世紀のサブカルチャーの中でも特に重要な役目を果たしたポップミュージックというジャンルについてのふたりの会話を通して、形にしたつもりだ。
各章は、1970年代以降のディケイドごとに選出された数名のアーティストについてのふたりの会話で構成されている。
第1章70年代編では、「カウンタカルチャーから切断されたロック」の先駆者としての矢沢永吉、プレ消費社会においていち早く「キッチュ」をお茶の間に届けた沢田研二、記号化される中で苛立ちと屈託を抱えることになった坂本龍一を。
第2章80年代編では、「ホンネ」と「悪意」の大衆スターとしてのビートたけし、女性として生きる中で抱えた不能感と軋みを表現してしまった戸川純、バブルに呆けた社会の中で、リズムによる救済を求めた江戸アケミを。
第3章90年代編では、相対主義的態度を出発点に「意志」と「感覚」に分派していったフリッパーズ・ギター、自意識過剰な「男子」たちのヒーローとなった電気グルーヴ、過剰な記号化と物語化を体現することになった存在としてのX JAPANを。
第4章ゼロ年代編では、戯れとしての記号遊びから国策にまで接続されることになった存在としての椎名林檎、ネオリベ時代に自らをレぺゼンしたラップスターKREVA、ロックにおける少年性を更新し、イノセントでベタな物語で支持を得たバンプ・オブ・チキンを。
2010年代編としての第5章では、「男子」の最新型としての可能性と限界を示す星野源、日本消費社会におけるポップス世界の最強最悪のゲームマスター秋元康、そして自分自身のキャラクターを、自らの手と視線で創り生み出す存在としての大森靖子を。
時にさまざまな横道に逸れながら、それぞれのアーティストが時代の中でどのように表現し、いかに振る舞い、そしてそれが社会においてどんな意味を生んだのかということを考え語り合った。
どれだけ過去を懐かしんでも、あの時代はもう帰ってこない。消費社会に引きこもり、サブカル消費に耽っていられる状況には戻れない。この国はもう「ナンバーワン」じゃない。その中で延々と戯れていられるような、欺瞞的な「平和」は、「戦後」は、もはやこの国には無い。
だが、だからと言って首相が語る「美しい国」の夢の中に取り込まれるのは癪じゃないか。そんなつまらない夢に騙されるほど、僕らは「消費者」としてもヤワじゃなかったはずだ。伊達に何十年もサブカルチャーを消費し続けてきたわけじゃない。サブカルの軌跡を辿ることで、サブカルの「後」の時代を考えることで、そのことをあらためて思い出そう。ポスト・サブカルチャーの時代へ向けて。
そして、スタートの前に、謝辞を。日々を共に過ごしているGの、世界や人間に対する真摯な姿勢からさまざまなことを学んだからこそ、僕はここまで歩みを進め、この本をつくることができた。ありがとう。尊敬しています。
それでは、そろそろ始めよう。
【recommend】
サブカル批評の焼け跡に立ち上がるルネサンス! でありながら、彼らの饒舌な対話が言論ゲームに陥っていないのは、そこで、我々の暮らす社会は何故こんなことになってしまったのか、そしてどうするべきなのかという精密な検証と誠実な議論が行われているからだろう。
---磯部涼
戦後サブカルチャー(あるいはポップカルチャー)のアイコンを、メディアを通じてプレゼンテーションされ消費される「キャラクター」として捉え、その系譜を編み直す。それはひとつの無謀な通史の試みであると同時に、生身の人間がつくりだす「キャラクター」を消費することの倫理と可能性を思考する土台でもある。サブカル的「オトコノコ」による、「オトコノコ」性の総括の記録。
---imdkm
スターやサブカルの歴史を記すならふさわしい当事者や研究者はほかにもいるだろう。でもこれは違う。いまここにいる〈私〉と〈社会〉の関係を考えるための一冊だ。語らいを続けよう。その在り処さえ危うい時代に。
---九龍ジョー
84年生まれ(私の20個下)という微妙に絶妙な世代ならではの射程の長いニッポン・サブカル・サーガ。
固有名詞縛りの各論として読んでも面白く、強い問題意識に支えられた半世紀にわたる通史としても読みごたえがある。
端的に言ってこれは、今は亡きわが国のサブカル(チャー)へのレクイエムだ。
だからこそ、いよいよ本気で新しい何かを生まれさせなければならないのだ、と著者たちは言っているように思える。
---佐々木敦
TVODは「歴史」にこだわる。それはサブカルの愛好と批評に半ば宿命的ともいえる弱点を補完する。80年代リアルタイマーなのに当時のあれこれを忘れてしまった年長者の私は、申し訳なさと感謝に震えた。
---高岡洋詞
日本のサブカルチャーは、音楽は、お笑いは、ポリティカルな事象を扱わないからダメだ、カウンターカルチャーたり得ていない、などと言う人は多い。だけど、なぜそうなったかをここまで丁寧に追うことができたのは、TVODのふたりが初めてなんじゃないか。
1970年代から2010年代まで、それぞれの時代を象徴するキーパーソンを徹底的に分析することで、たとえばポップスターが自らを記号化したことが世の中にどんな影響を与えたかだったり、前時代の価値観へのカウンターとして機能していた存在がやがて前提が失われて変質していく過程だったりが見えてくる。
そして最終的に、自分自身も戦後サブカルチャーの典型的な子供のひとりにすぎないんだっていうことに気づかされる。
---ハシノイチロウ(LL教室)
モヤモヤと感じていたことに的確な言葉が与えられていく快感。こんなラジオ番組を作りたい!と悔しくなるくらい。僕より10歳若いおふたりですが、後ろからしか見えないこともある、と痛感しました。
---長谷川裕(TBSラジオ:「文化系トークラジオLife」「菊地成孔の粋な夜電波」「荻上チキ・Session-22」など)
1984年生まれのふたりが焼け跡になってしまった日本で 未来への武器を探しながら紡いだ「サブカル」の精神史。
---姫乃たま
渋谷PARCOから本屋が消え、ヴィレッジヴァンガードが郊外のショッピングモールに溢れた(それすら飽和して久しいが)時代の「サブカル」とはなんなのか。遅れてきた(けど、ギリギリ間に合ってしまった)サブカル青年たちによる、ミュージシャン・バンドのキャラクター性から時代を読み取る試みは、「後追い」ならではのスリリングな切れ味をみせる。
既存のサブカル音楽評論では、手薄になりがちだった矢沢永吉やX JAPANら「ヤンキー」への目配せも「キャラクター」にフォーカスしているからこそ。「失われ続けた」と呼ばれ続け、もはやそれが日常になってしまったこの30年。経済の豊かさに担保されていた、かつてのサブカルのようにはいられない。現実は厳しいし、サブカルはもはや貧しい。「焼け跡派」というのは、きっとそういった現状と向き合うことなのだ。
---藤谷千明
TVODとは会って話した瞬間に意気投合しました。この社会に対峙しつつ、この社会を乗り越えるものとしての音楽ーーその可能性を精一杯に信じる姿勢には、同じアーリー80’s生まれとして圧倒的に共感!
---矢野利裕
80年代以降の日本の「サブカル」に至る流れというものを考えた場合、「世界と自分の間には社会が存在しているという当たり前のことに目を向けることなく、自意識のゆりかごを育てていく行為でしかなかったのかもしれない」という考えが浮かぶ人も少なくないだろう。社会と訣別するのでもなく、社会と闘うのでもなく、無意識に自然とないものとして目をそらすことができたのは、かっての日本が金があったからに過ぎない。日本の「サブカル」にみられる反権威、反体制的なものの多くは、身体的な生存の意志に乗っ取ったものではなく、親の庇護下にある子供がいたずらをして満足するような、「他人とは一味違う自分」という自意識を満足させるためのものでしかなかったのかもしれない。社会に守られているのが前提の遊びだったのかもしれない。終わらない日常などないということを人々が気付きだしたのは、あの大地震以降だろう。いや、既に崩壊は始まっていたのだが、それは緩やかすぎて多くの人は気づいていなかった。それがあの日以降、速度が急速にあがることで、対峙せざるを得なくなったはずだ。また、社会の存在を意識する中で男性は今まで無意識に続けてきた「男の子たちの遊び」が孕んできた問題に気付かされることにもなった。ジェンダー問題と無縁でいられる時代は終わっている。
遊びの時間は終わったのだろうか?その答えはYesであり、同時にNoでもある。守られたエリアでの他人との差異化のゲームを続けることはできない。そのゲームが終わってることに気付かないまま続けている人もいれば、ゲームを続けるために庇護下にいれそうな領域や、ネットのポピュリズムの世界に逃げ込んでいく人もいる。しかし、あのゲームは終わったのだ。
TVODのふたりが提唱しようとしていることを自分なりに解釈すると、社会の流れと対峙しながら共同体的な安全領域に逃げ込むことなくあくまで個人単位で新しい「遊び」を始めようということ、それを続け続けようことなのではないかと思う。かっての「サブカル」の歴史が産んだものは負の遺産ばかりかというと、そうではないだろう。彼らがこの本でやっていることは検証であり断罪ではない。これから先に続けていくための確認作業である。置いていくべきものもあれば、持っていくべきものもある。
かっての無自覚な差異化のゲームの中で焦土と化した日本のサブカルの跡地で、若くもないドン・キホーテ二人組が再生をかけた闘いを挑んでいる。それは過去の再現を目指すものではない。その先にいくための闘いであり、新しい何かを求める闘いだ。それは無謀であるかもしれないが、そんなことを考えても仕方がない。彼らは最初の一歩を踏み出したのだし、それが一番重要なのだから。
---ロマン優光
(敬称略;五十音順)
